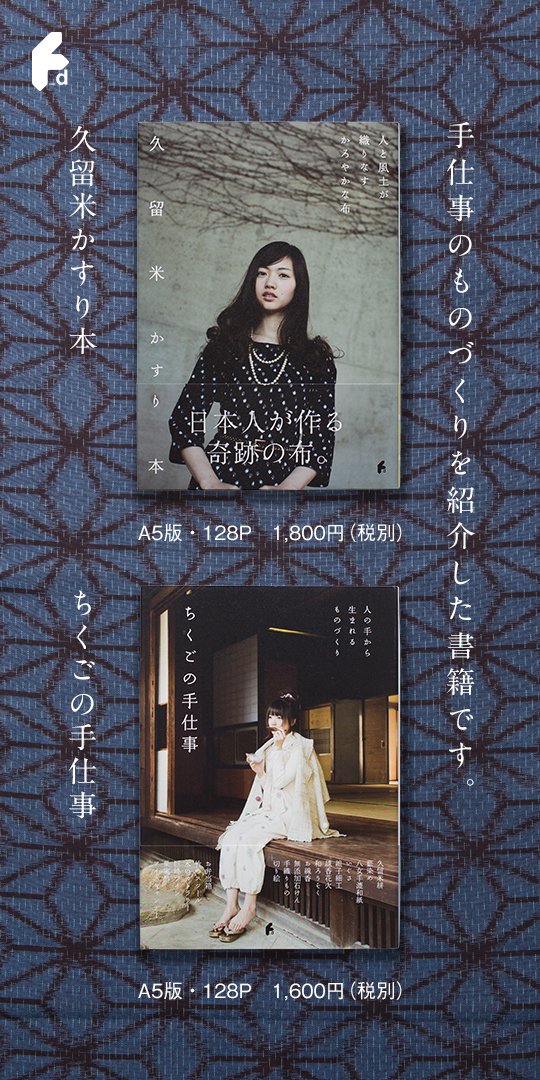久留米絣と糸のこと

糸をタテとヨコに織り合わせたものが、生地となります。久留米絣では、糸をあらかじめ生地の柄に合わせて括り染色してから、織りの工程に進みます。生地のはじまりとなる糸についてお話しましょう。
久留米絣が作られる以前の江戸期、久留米藩では綿花の栽培が盛んでした。久留米藩領地・筑後川流域でとれた綿花を紡いだ糸で作った織物が、後に久留米絣として発展したのです。紡績技術の進歩により、手紡ぎの糸からスタートした久留米絣も、今ではいろんな糸が使われるようになりました。

はじめは1本の糸同士を織り合わせていたものが、2本の糸を縒ったものも織り合わせられるようになりました。2本の糸を縒った糸の生地は、1本の糸の生地よりも丈夫です。1本の糸の生地は、2本の糸を縒った生地より柔らかです。
現在は、1本の糸を「単糸 タンシ」2本の糸を「双糸 ソウシ」と呼び、用途に応じて使い分けられています。
糸の太さも様々で、太い糸では厚みのある生地、細い糸では薄手の生地が織り上がります。糸の太さは「番手 バンテ」という単位で呼ばれており、一般的な糸の太さが30番手です。この30番手を中心に小さな数値は太い糸、大きな数値は細い糸となります。

タテ糸が60番双糸、ヨコ糸が20番単糸の久留米絣。とても細い2本の糸がタテに、やや太めの1本の糸がヨコに使われており、軽くて柔らかな生地です。

タテ糸が60番双糸、ヨコ糸が10番スラブ単糸の久留米絣。とても細い2本の糸がタテに、太さに変化のあるの1本の糸がヨコに使われていて、表面に立体感のある柔らかな生地です。
このように、使われる糸によって生地の風合いは変化します。
その他にも、粒感のあるネップ糸、太さに変化のあるスラブ糸、綿以外の素材の糸など、いろいろな糸で久留米絣は織られています。糸の太さや強さに合わせて織機を調整することも、久留米絣の職人さんの腕の見せ所なのです。